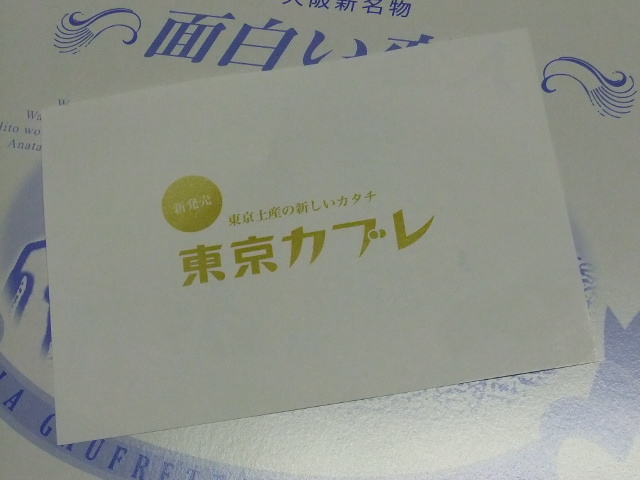2011年11月29日(火)
短編小説「一切れのパン」を急におもいだしたのは、震災の日のことでした。
中学校だったでしょうか、国語の教科書で読んだ、第二次世界大戦ヨーロッパでの、ナチスの支配と逃走のなかの、
ちいさな、わすれがたいものがたり。
ドイツにとって急に敵国人となった主人公のわかものが、収容所へはこばれる列車からスキをついて逃走するとき、
列車に残るユダヤ人ラビ(ユダヤ教教師)からちいさな包みを受け取ります。
ラビは小さいハンカチの包みを差し出した。
「この中には、パンが一切れ入っています。何かのお役に立つでしょう」
私は感謝しながら包みを受け取ったが、ラビはまだ、車両の開いた口から去ろうとしない。
「まだ何か….」
「あなたに一つだけ忠告しておきましょう。そのパンは直ぐに食べず、できるだけ長く保存するようになさい。
パン一切れ持っていると思うと、ずっと我慢強くなるもんです。
まだこの先、あなたはどこで食べ物にありつけるか分らないんだから。
そして、ハンカチに包んだまま持っていなさい。
その方が食べようという誘惑に駆られなくてすむ。私も今まで、そうやって持って来たのです」
汽車は動き出した。私はもう、彼に感謝する暇もなかった。
(ムンテヤーヌ作・直野敦訳)
中略・・・・
最後に彼は、生きて妻のもとに帰ります。
やっと家に辿り着いた時、私はもう妻の質問に答える元気もなかった。
長椅子に崩れ落ちるように横になったが、眠れもしない。
料理の匂いが鼻をくすぐる。
私は、あのユダヤ人のラビからもらったパンを思い出して、ポケットからハンカチの包みを引っ張り出し、
微笑しながら包みを解いた。
「これが僕を救ったんだよ….」
「まあ、その汚らしいハンカチが?何がその中に入ってるの」
「パン一切れさ」
突然、部屋全体が私と一緒にくるくると回転し始めた。
ハンカチからぽろりと床に落ちた一片の木切れ以外には、もう何にも私の目に入らなかった。
「ありがとう、ラビ」
(作、訳、同)
3月11日、地震に遭ったのは恵比寿駅のホームでした。
至光社の打ち合わせのかえりで、原画を一式もっての大荷物、こんどの本の絵にほとんどオッケイがでてうはうはしており、
しかも、次の本の予定もきまってかなりうかれておりました。
そのとき、ホームにはまばらにしか人はおらず、
ビルがぎちぎちと音をたてて揺れるのをなすすべなくながめ、頭上の安全を気にしながら柱につかまり、
ゆれがおさまって歩きだそうとしたときには、柱から離した手が震えました。
どこの、どんな地震かもわからないまま、列車が一晩中うごかないとも予想せず、しばらく運行再開を待ちましたが、
無事を確かめあったあと家族とも連絡が取れず、東北が、あのようなたいへんなことになっていたことも知らず、
住まいのある町にも津波の警報が出ていることも知らず、考えたことはこんなことでした。
・・・電車が動く頃はもはやラッシュだわ。原画もって満員電車にのるなんざ迷惑千万。
う~。オッケイ出たんだ、捨てていけるか。ここはひとつ、面倒でも至光社にもどり、あずかってもらお。
駅をでて、バスを待つひとたちの長い列を横目にすたすたと足早にあるくこと10分あまり、
至光社にたどりつくと、スタッフ皆さまはかなりわあわあと、
ああ、いた、とか無事だったかとか、よく戻ってきた、とか口々にいいながら、手をとったりさすったりしてくださり、
たいへんなことになっている、もうみんな帰宅する、品川までなら車で行けそうだから送っていく、と、
はぎとるように原画をあずかってくださったかと思うと、
ほらほら、と戻す手には非常用の水のペットボトル、それから、
「ひとつあまいものがあるともつからね、ちょうどもらいものがあるから。」
と、あのみんな知ってる北海道銘菓、ひとひらの「白い恋人」をくれたのでした。
いつもの在宅労働者が都内にいると知って親族がてんやわんやしたり、
たまたま海外にいた長男がいちはやくなにもかもを心配してきたり、
ぷっつり連絡のとれなくなったいなかもののおくさんがひとりで都内を徘徊しないよう、
だんなが念じつづけていたりしたらしいけど中略。
けっきょく、その日は帰宅できませんでした。
品川のホテルのロビーで、至光社の、やっぱり神奈川県民のスタッフYさんとふたり、
おたがい翌日都内にのこっている家族と合流してかえることにして、
しかたなく、落ち着きました。
ロビーの片隅で、テレビが様子を伝えているようでしたが、落ち着くことのできたソファを離れないことを優先しました。
「なにかしらの同心円」が見えましたが、なんのことをいっているのか、わかりません。
海辺の自宅にのこっている子どもらと連絡を取るのに精いっぱいになっているうち、携帯電話の電池も尽きました。
きゅうにおなかがすきました。
ホテルのスタッフさんにおしえてもらってコンビニへひとりで、
徒歩で帰宅なさる都内勤務の多くのみなさまの大河のようなながれをかきわけでかけてみると、
食料は払底、ちいさなひとくちチョコレートを、やっと買えました。
「まあ、『白い恋人』があるからね、ほら、『一切れのパン』ってやつよ。
あれはもう、限界まで食べちゃ駄目だね、きめたよ、もう。がまんがまん。」
なんてことを考えながら、至光社Yさんとちまちまチョコを食べたり、
居合わせた見ず知らずのかたがたとおしゃべりして不安をわかちあったり、
ところでこのホテルは、宿泊客でもないのにひとばんここにいさせてくれるだろうか、という心配をしたりしながら、
くりかえし余震でゆれるシャンデリアをだまって見上げたりするうち、ホテルが、
ほんとうに感謝しているのですが、品川のプリンスさくらタワーさまが、
宴会場に寝具を用意する、どうぞお休みください、と案内してくださり、もはや寝るしかない、となったとき、Yさんと、
じゃ、たべよっか、「白い恋人」。
と取り出して、しげしげと、まず、ながめてみたところが。
ねえ、これ、「白い恋人」じゃないよ。
え?ああっ!
「面白い恋人」って書いてある!
ああっ!!!!!なななななんだ、そら!
大阪だ!
ああっ!吉本興業だ!
なんだなんだなんだ。
空腹を抱えてひとしきり笑いました。
わらったら、すこし、元気がでました。
シャンデリアが、ぐらぐらとゆれました。
ありがとう、面白い恋人。
そのときの包装個袋は、まだここにあります。

なんで「平成日本『一切れのパン』・ありがとうラビ」を、
またきゅうに思い出したかっていいますと、
白い恋人と面白い恋人が商標をめぐって裁判するそうで、
ぜひなかよく解決していただきたい
、販売地域も競合せず、しかもどっちもおいしいじゃないですか、
白い恋人はもちろんいつだって北海道みやげに買ってきてるけど、
だんなの大阪出張土産はいまじゃあ面白い恋人なんだけどなあ。
しかも、面白い恋人の箱の中には、
別製品の宣伝紙片がいちまいはいっていてまた爆笑。
わらいのお土産、家庭円満、もういちどいう、なんどでもいうよ、
ありがとう、ラビ。
こうなったら粋な判決、おもしろい和解案、さあ出て来い。